射水の観光スポット
新湊大橋
射水エリアでまず行くべき場所は、新湊大橋でしょうか (ツアーでは、橋を渡るときに天気がよければ立山連峰が見えるというのがウリ)→ そして「きっときと市場」で昼食など。
個人でだったら、海王丸パークに行きたいですかね (上記の画像 左には「恋人の聖地」モニュメント)。
ですがもっと行きたい・行った方がよいスポットは↓↓↓ (なんとツアーには入っていなかった)。
新湊内川

 「日本のベニス」と呼ばれるこの内川エリアは、川の両岸に漁船が係留し、昔ながらの家々が建ち並ぶ、なんともノスタルジックな雰囲気の風景です。
「日本のベニス」と呼ばれるこの内川エリアは、川の両岸に漁船が係留し、昔ながらの家々が建ち並ぶ、なんともノスタルジックな雰囲気の風景です。
各橋上からの景色&川沿いの散策 (お店もある) がもちろんメインの楽しみ方ですが、1本北に入った通りにも歴史的建造物並みの木造住宅が建ち並んでいてすごいので是非行かれた方がよいです。
この内川も、岩瀬と同じ「北前船」の中継地として栄えた町ということで、歴史があるのですね。




 吉久
吉久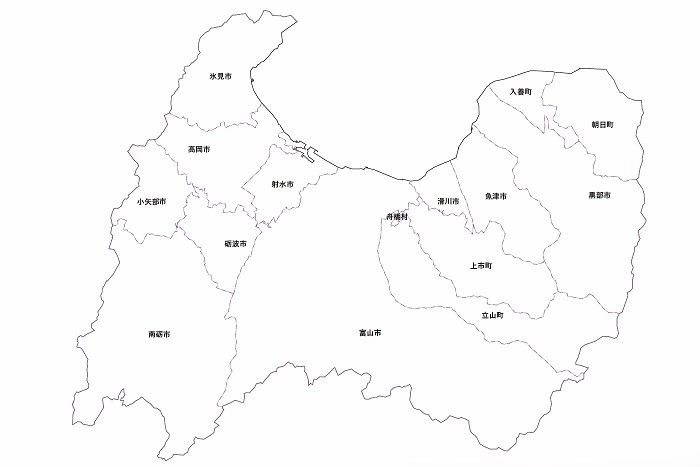



 この市電、何が面白いか?って私を惹きつけたのは、
この市電、何が面白いか?って私を惹きつけたのは、



 万葉線では、六渡寺の手前 (北へ川を渡ればすぐ伏木港)。
万葉線では、六渡寺の手前 (北へ川を渡ればすぐ伏木港)。
 ツアーでも必ず立ち寄る、言わずとも知れた名所。
ツアーでも必ず立ち寄る、言わずとも知れた名所。


